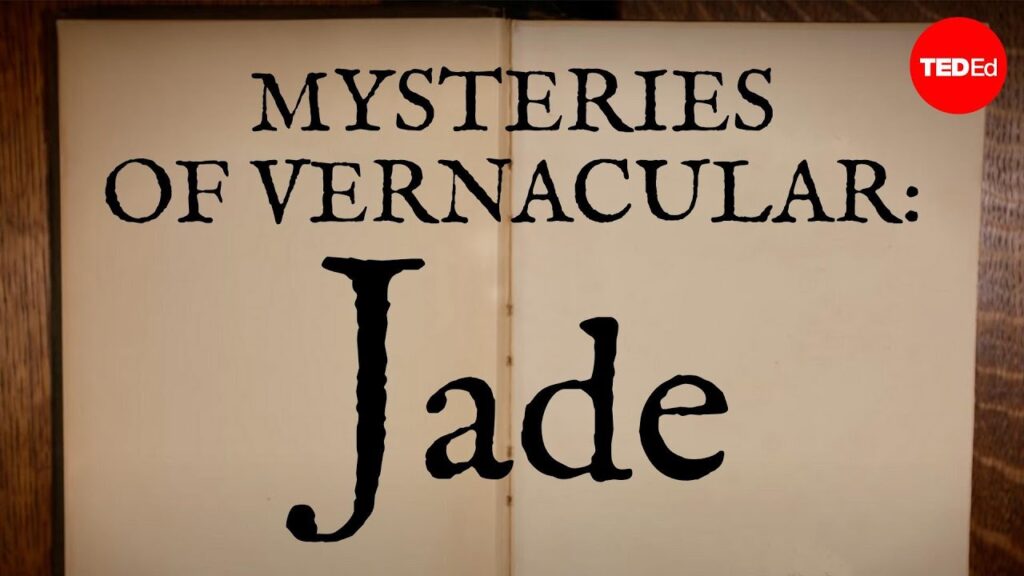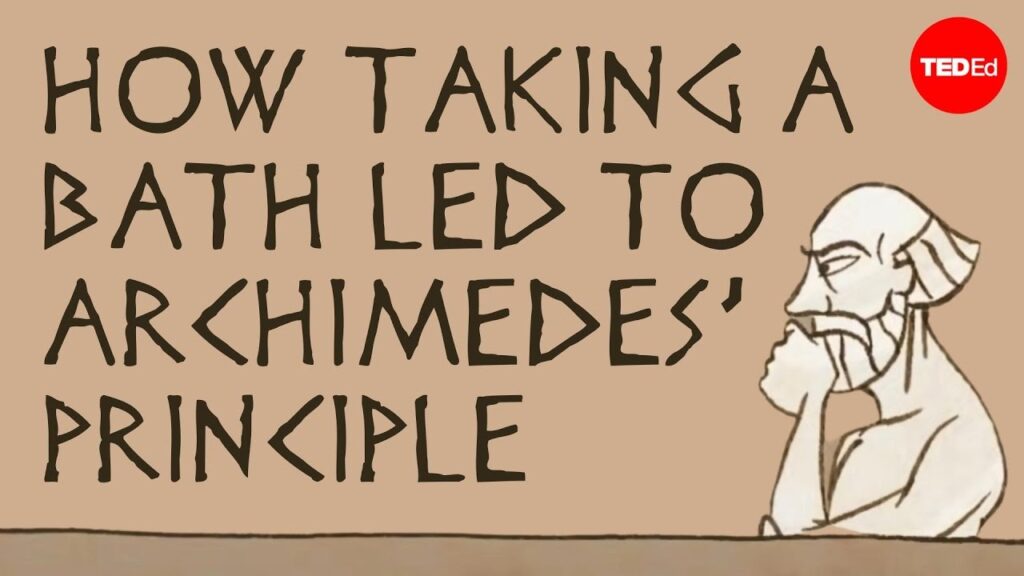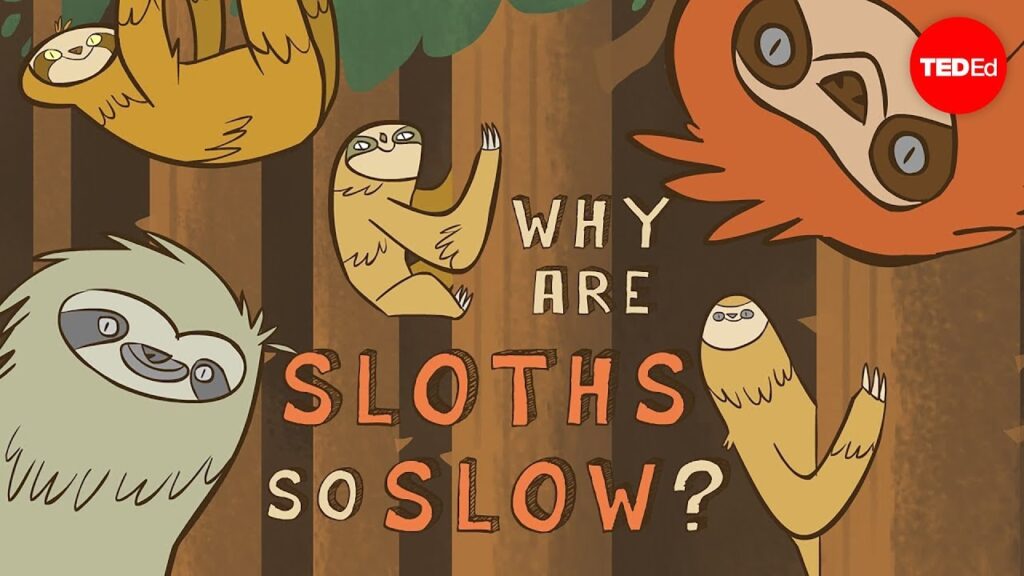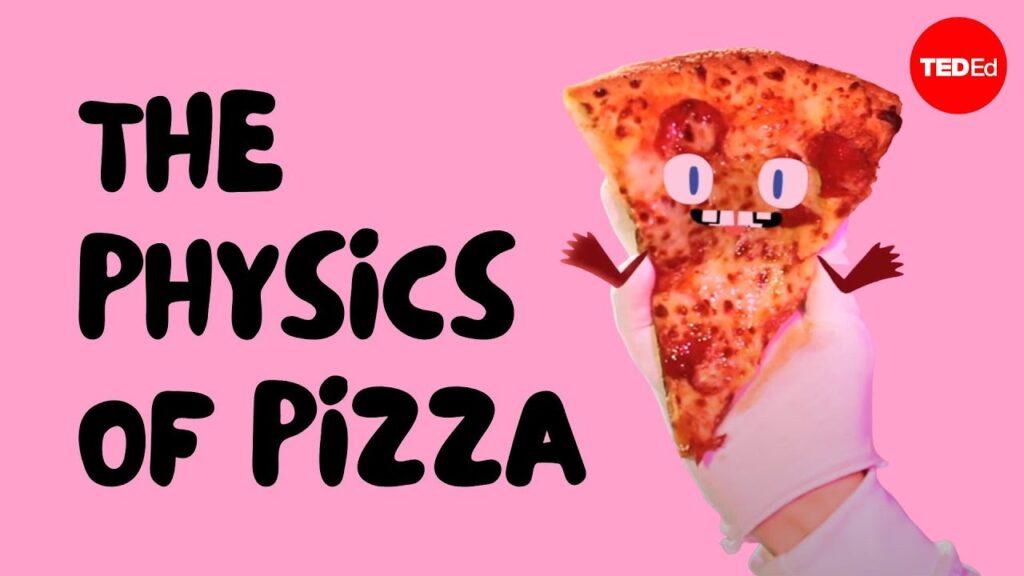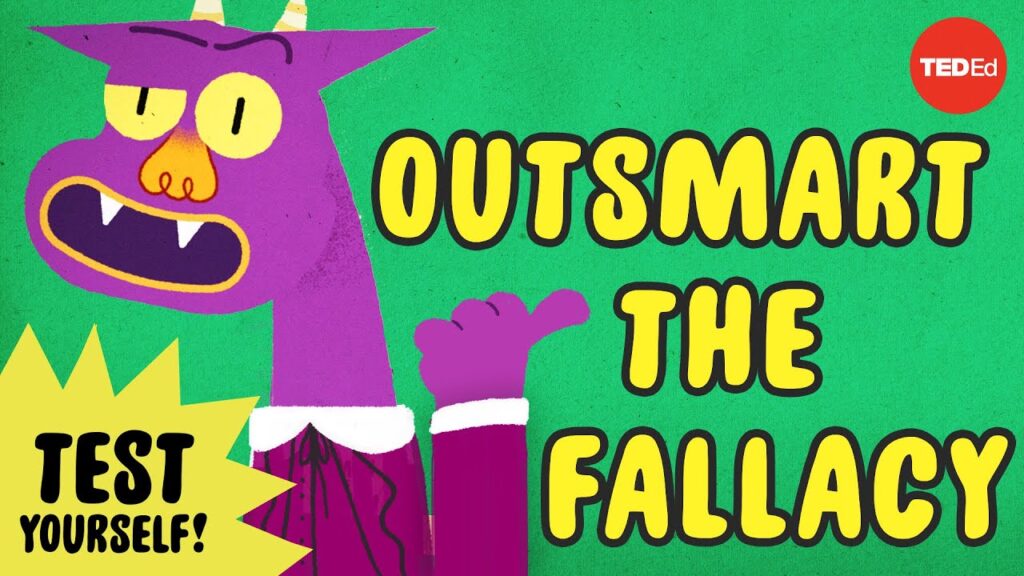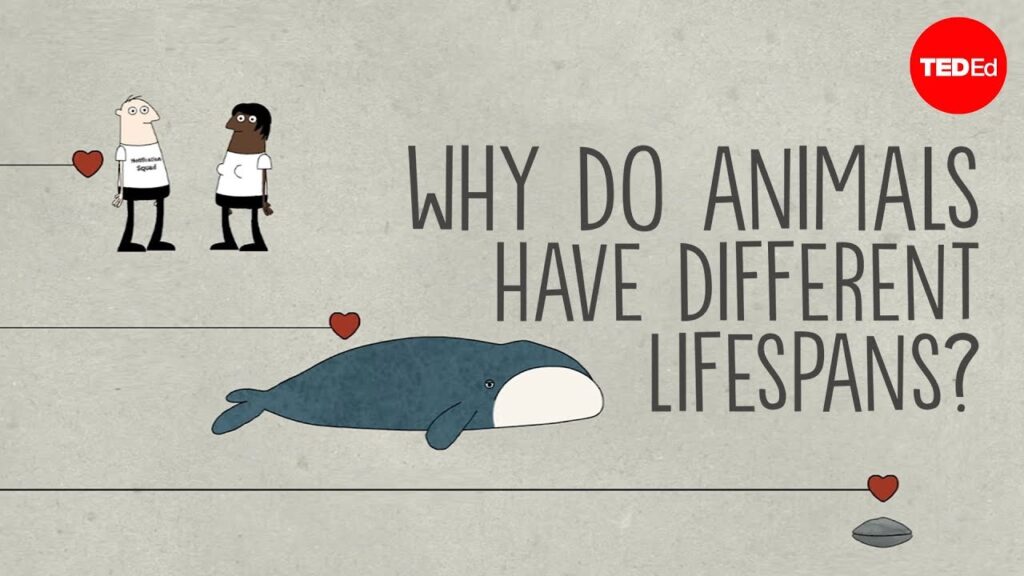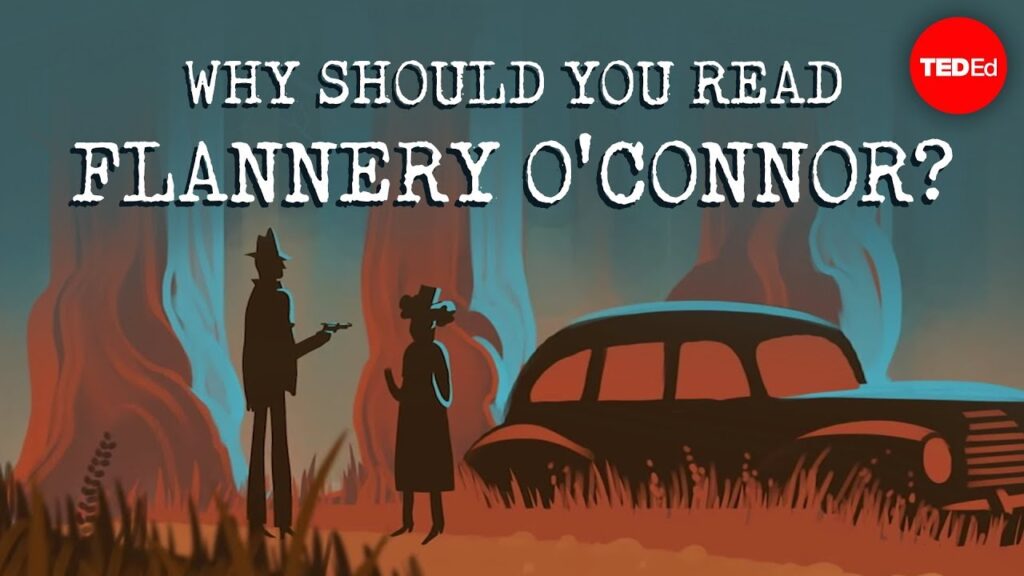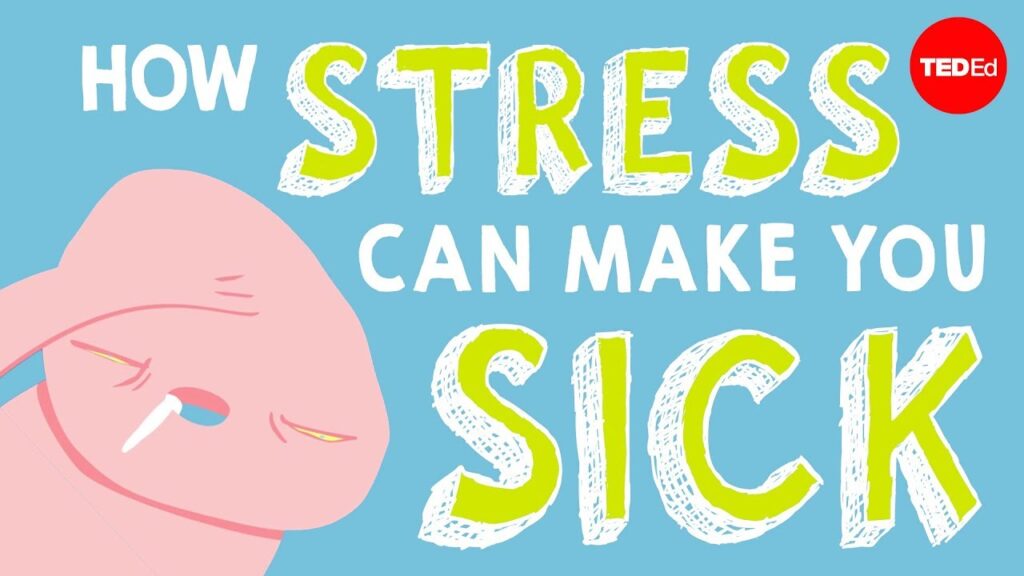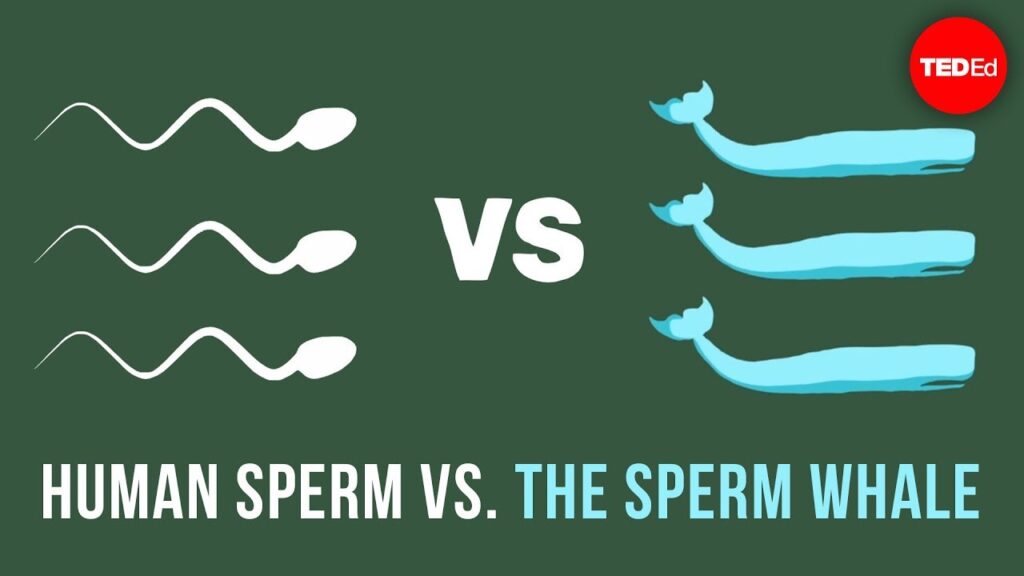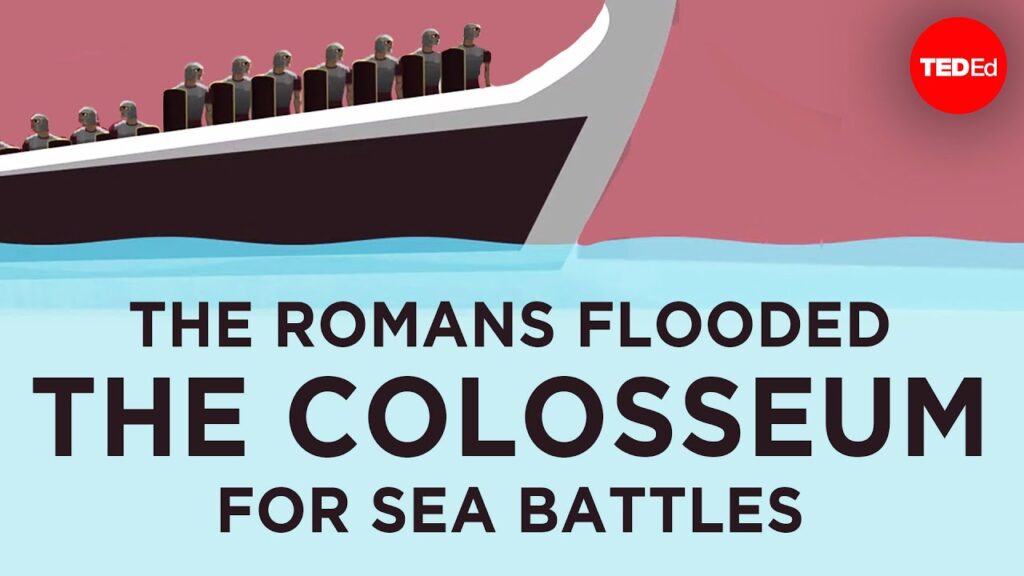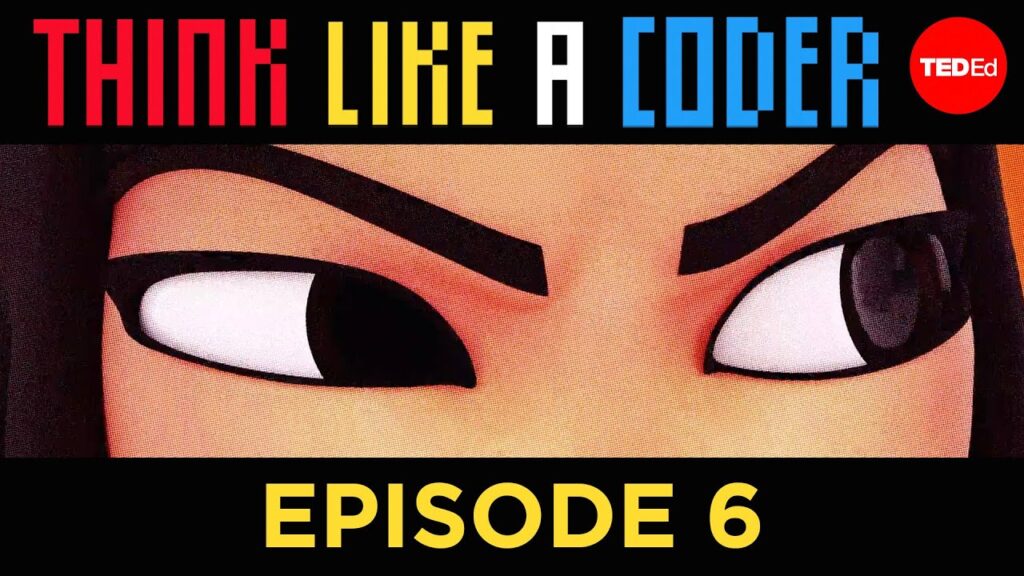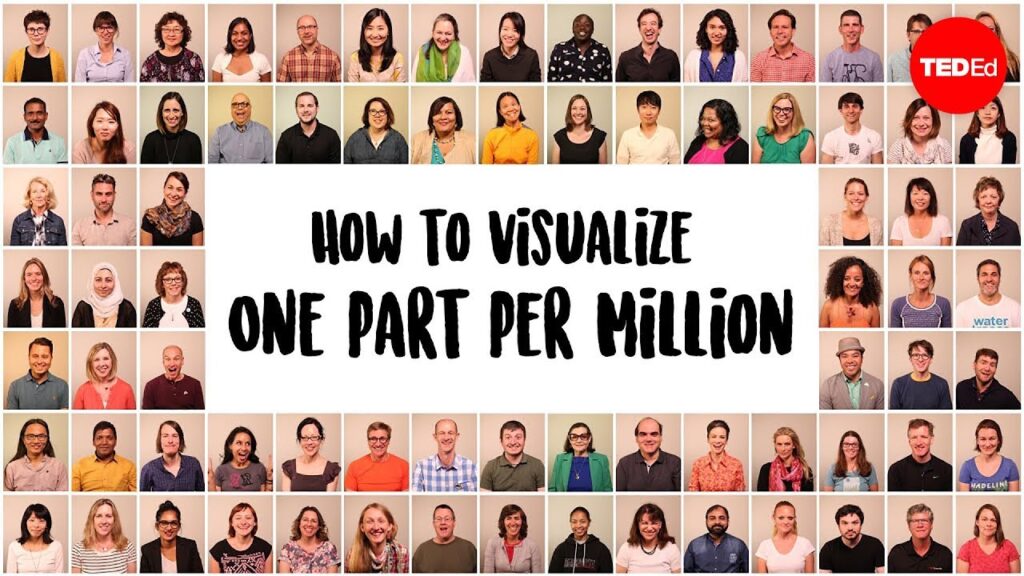普遍文法と言語習得の持続的な謎
概要
本記事は、1950年代初頭にノーム・チョムスキーが提唱した普遍文法の概念について掘り下げています。この理論によれば、人間の脳は、すべての言語に共通するとされるある種の内在的な文法ルールに従って言語を処理するようにハードウェア化されています。本記事では、この理論の妥当性を分析し、普遍文法の2つの主要なコンポーネント、つまりすべての言語に共通する文法ルールが実際に存在するかどうか、そしてこれらのルールが脳にハードウェア化されているかどうかを検討しています。また、チョムスキーの修正された原理とパラメーターの理論、そして再帰という1つの共有原則のアイデアについても探究しています。さらに、本記事は脳内の内在的な言語機能の概念についても議論し、チョムスキーの提案する特定の孤立したエンティティであるという見解に疑問を投げかけています。
目次
- すべての言語に共通する文法ルールは存在するのか?
- 普遍文法と脳の関係はどうなっているのか?
- 世界中の言語の多様性については?
- 普遍文法の理論を洗練させる:原理とパラメーター
- 1つの共有原則 – 再帰
- 脳内に本当に内在的な言語機能があるのか?
すべての言語に共通する文法ルールは存在するのか?
ノーム・チョムスキーの普遍文法の理論によれば、すべての言語に共通する内在的な文法ルールが存在し、人間の脳はこれらのルールに従って言語を処理するようにハードウェア化されています。これらのルールによって、私たちは幼少期から無限の数の文を母語で作り出すことができます。チョムスキーは、普遍文法ルールを確立するための分析ツールとして生成文法を提案しました。しかし、各言語の構造をマッピングすることは非常に複雑で、各言語から多くのデータが必要です。チョムスキーの早期の普遍文法の理論は、より多くの言語学的データが収集・分析されるにつれて、各言語が大きく異なることが明らかになったため、かなりの挑戦に直面しました。
普遍文法と脳の関係はどうなっているのか?
チョムスキーが最初に普遍文法を提唱した当時、多くの言語にはその理論を支持するための十分なデータがありませんでした。しかし、より多くの言語学的データが収集・分析されるにつれて、言語学習に必要な生物学的な機構が存在することが明らかになりました。多くの科学者は現在、言語に責任がある生物学的な機構は、特定の孤立した言語機能ではなく、他の認知の側面にも関与する可能性があると主張しています。
世界中の言語の多様性については?
世界中の言語は大きく異なるため、どの文法ルールが普遍的であるかを確立することは困難です。チョムスキーは、1980年代に自身の理論を改訂し、すべての言語がある種の文法的原則を共有しているが、パラメーターによって異なる可能性があると提唱しました。たとえば、原則はすべての文に主語が必要であるということですが、パラメーターによっては主語を明示的に述べる必要があるかどうかが異なる場合があります。
普遍文法の理論を洗練させる:原理とパラメーター
チョムスキーの修正された原理とパラメーターの仮説は、すべての言語がある種の文法的原則を共有しているが、パラメーターによって異なる可能性があるというものでした。この理論は、言語の大きな違いを収容しようとしましたが、まだ決定的な証拠が欠けていました。
1つの共有原則 – 再帰
2000年代初頭、チョムスキーは、再帰という1つの共有原則しかないという考えを提