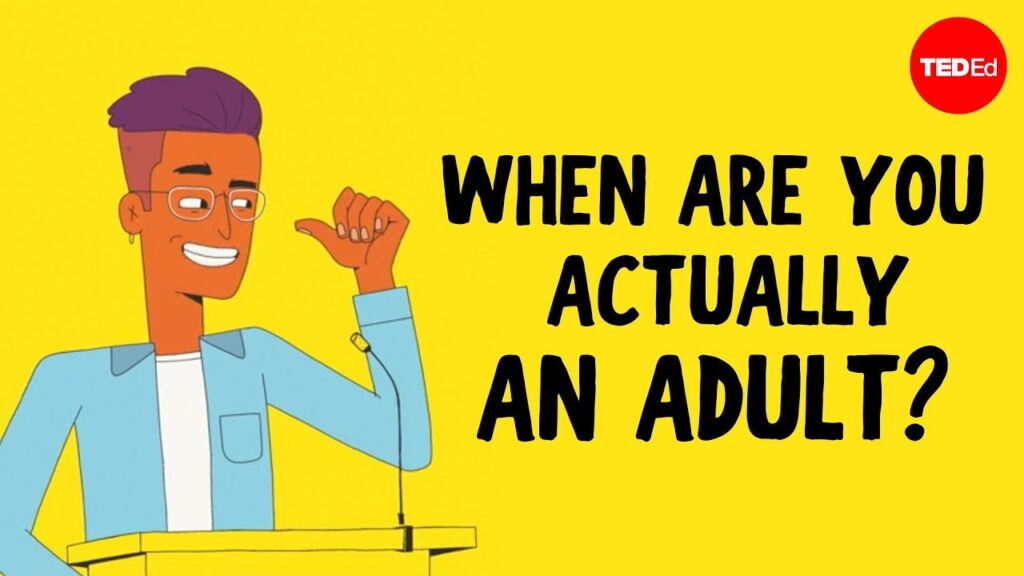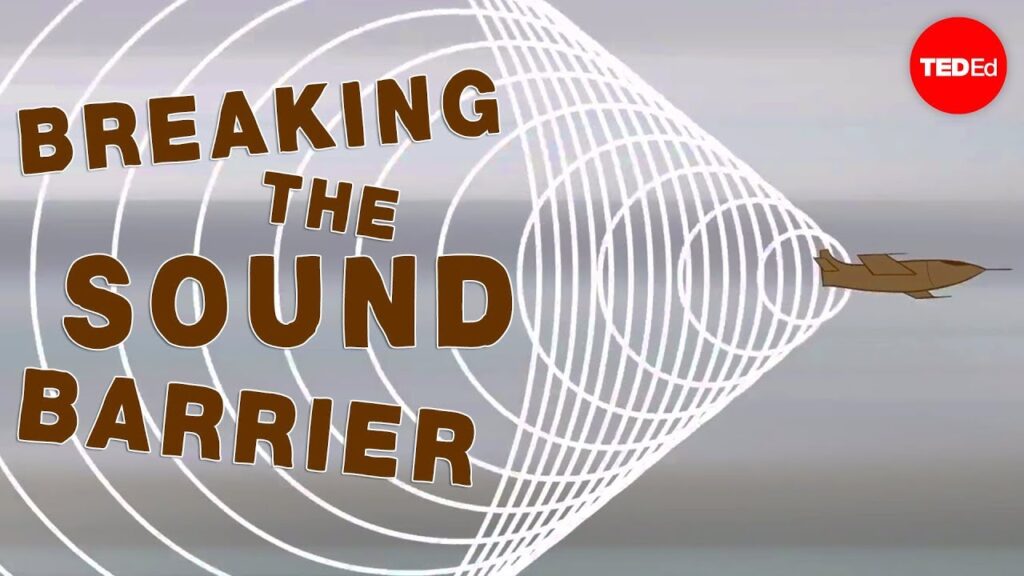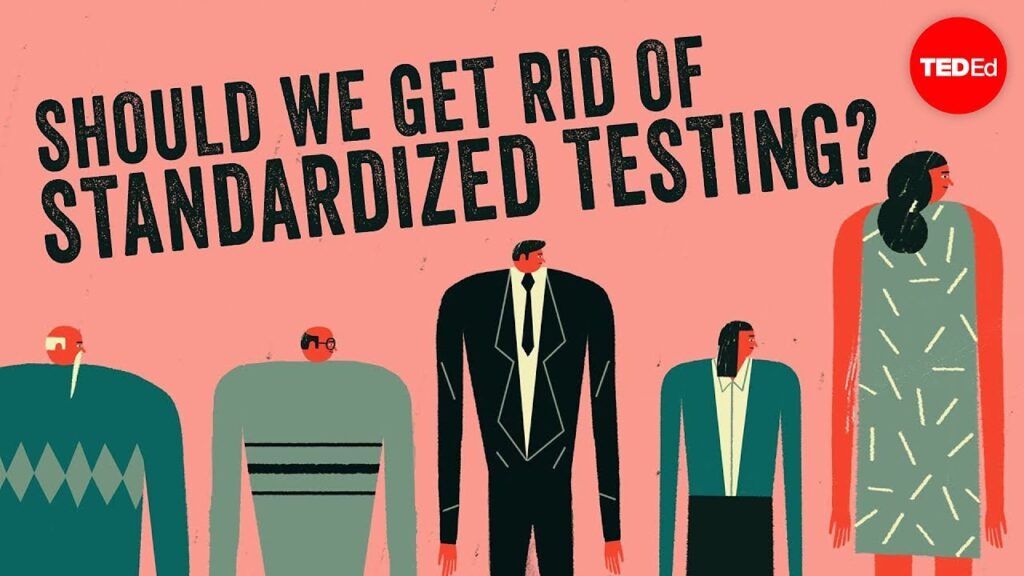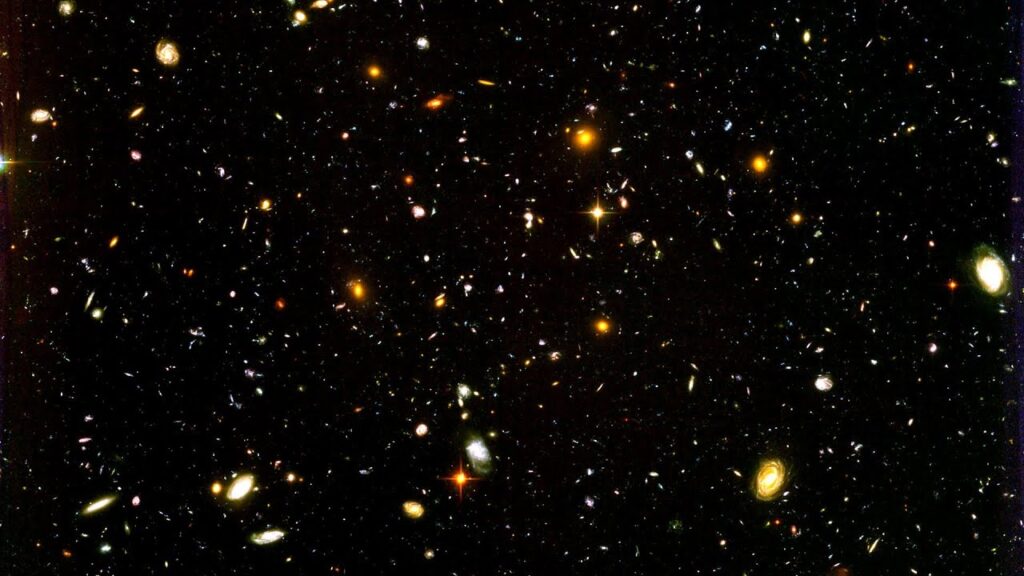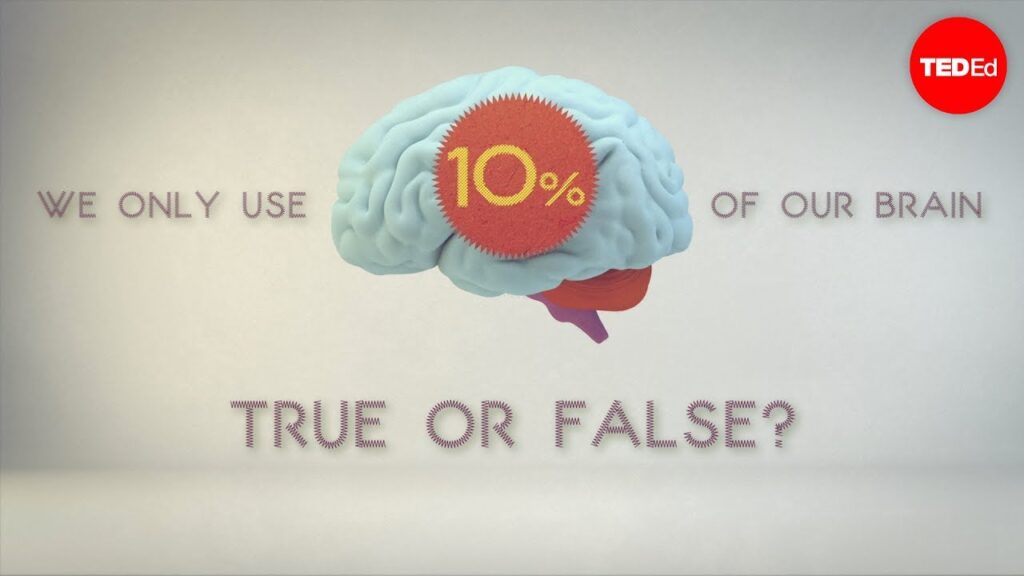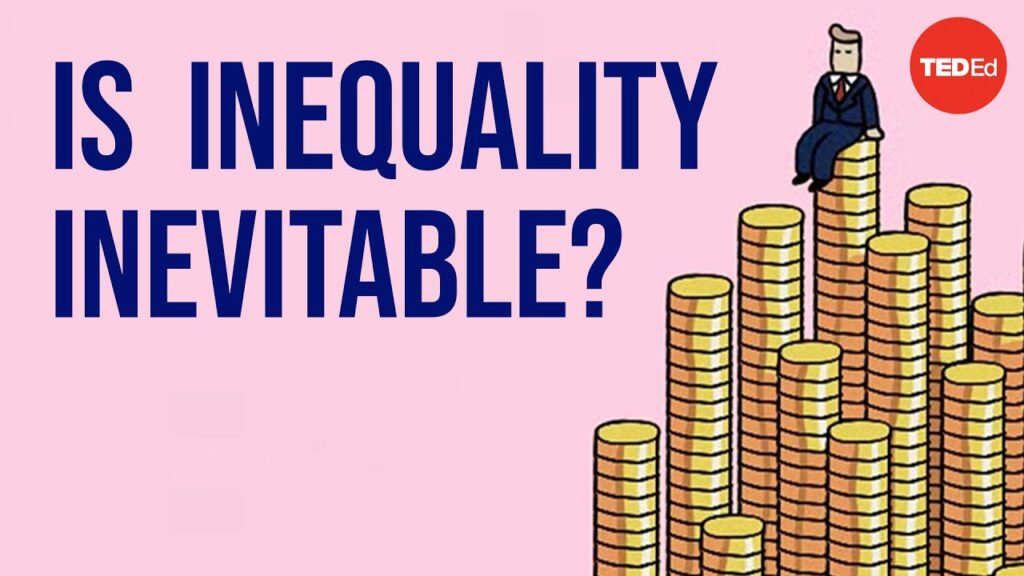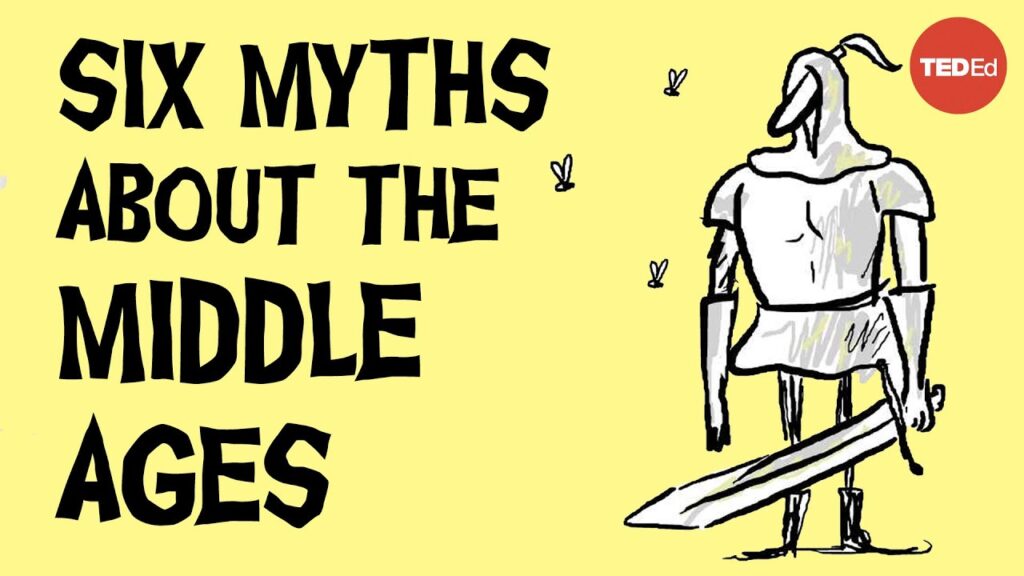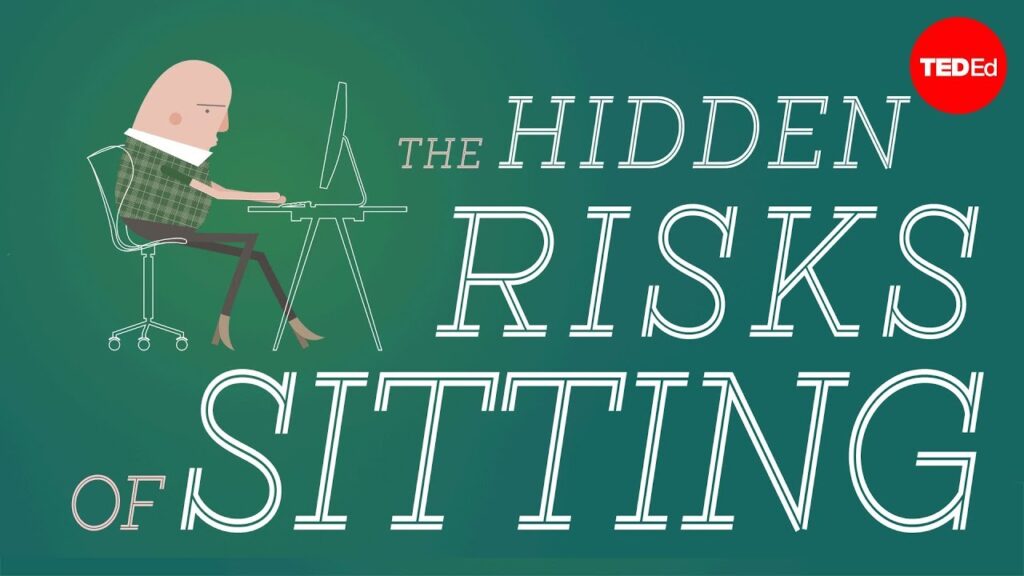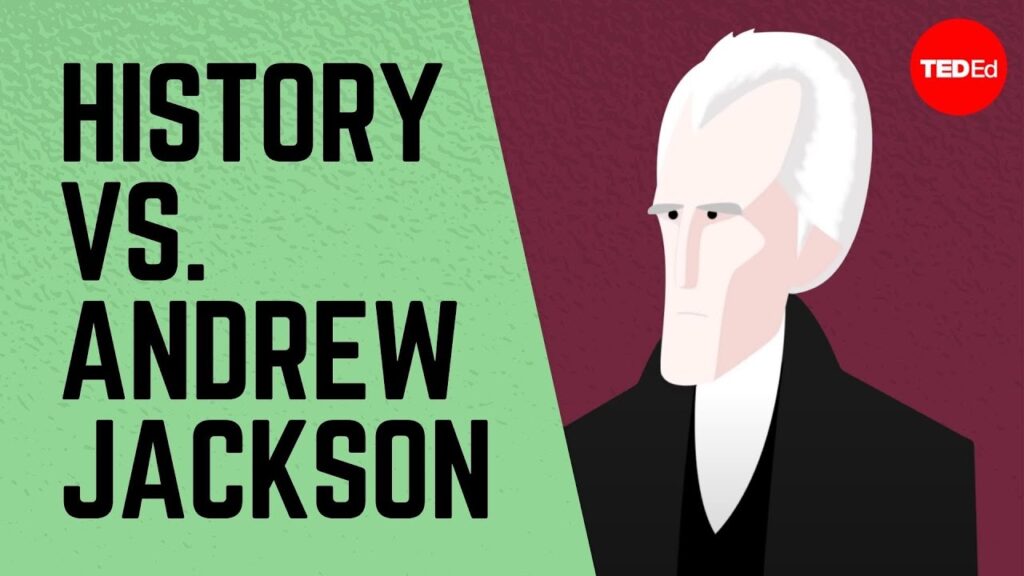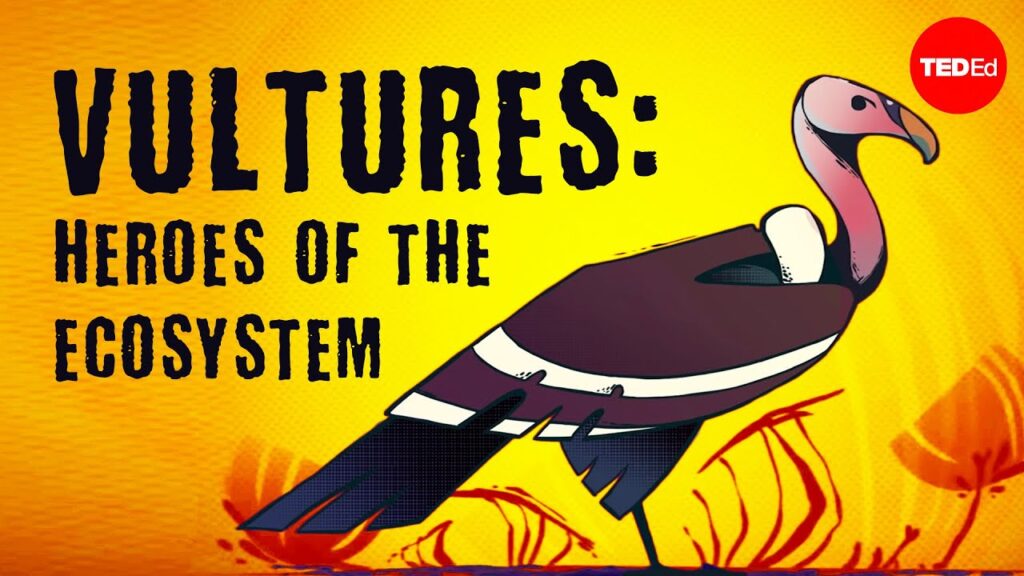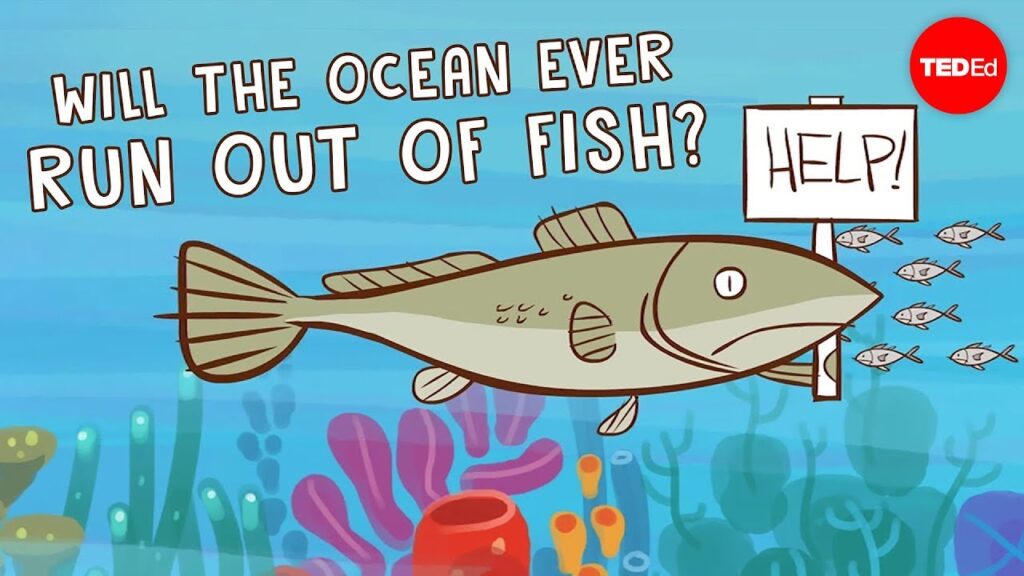抗うつ薬の進化:結核治療から化学物質の不均衡理論へ
要約
本記事では、1950年代の偶然の発見から1980年代の選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)の開発まで、抗うつ薬の進化について追跡します。また、これらの薬剤の発見から生じた化学物質の不均衡理論と、うつ病を説明する上での限界についても検討します。これらの限界にもかかわらず、米国の成人の約10%に影響を与えるうつ病を治療するための有効なツールがあります。
目次
- 抗うつ薬の偶然の発見
- 化学物質の不均衡理論
- SSRIsの開発
- 化学物質の不均衡理論の限界
- 結論
抗うつ薬の偶然の発見
1950年代に、イプロニアジドとイミプラミンという2つの薬剤が抗うつ効果を持つことが発見されました。イプロニアジドはもともと結核の治療に使用されることを意図されていましたが、イミプラミンはアレルギーの薬剤として開発されました。両方の薬剤は、モノアミンと呼ばれる神経伝達物質の一種に影響を与え、うつ病の化学物質の不均衡理論を導きました。
化学物質の不均衡理論
化学物質の不均衡理論は、脳のシナプス内のモノアミンが不十分であることがうつ病の原因であると提唱しています。イプロニアジドやイミプラミンなどの抗うつ薬は、脳内のモノアミンの利用可能性を増やすことで、このバランスを回復すると考えられていました。しかし、これらの薬剤には頭痛、眠気、認知障害などの副作用が多くありました。
SSRIsの開発
1970年代に、研究者たちは最も効果的な抗うつ薬がセロトニンという特定のモノアミンに作用することを発見しました。これが、1987年にフルオキセチン、またはプロザックとして開発された理由です。プロザックは、セロトニンの再取り込みを阻害する新しい薬剤クラスである選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRIs)の最初のものでした。プロザックのようなSSRIsは、古い抗うつ薬よりも副作用が少なく、よりターゲットされた薬剤です。
化学物質の不均衡理論の限界
化学物質の不均衡理論は、うつ病を理解するための重要な突破口でしたが、限界があります。うつ病を持つすべての人がSSRIsに反応するわけではなく、他の神経伝達物質に作用する薬剤に反応する人もいれば、薬剤に全く反応しない人もいます。また、抗うつ薬がなぜ効果的であるのか、また、薬剤を中止した後にうつ病を再発しない患者がいるのかはわかっていません。
結論
うつ病は、まだ完全に理解されていない複雑な疾患です。化学物質の不均衡理論には限界がありますが、SSRIsのような有効な抗うつ薬の開発につながりました。今日では、多くの人が抗うつ薬だけで治療されていますが、心理療法と薬剤の併用がより効果的です。うつ病を理解するためにはまだまだ努力が必要ですが、それでもうつ病を治療するための有効なツールがあります。